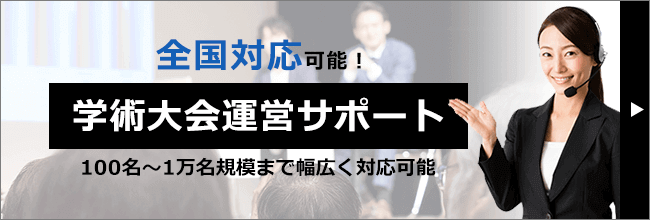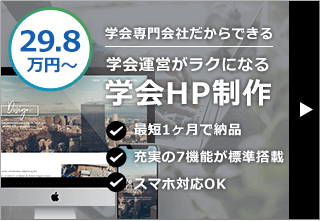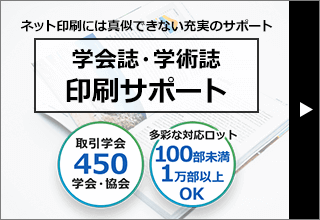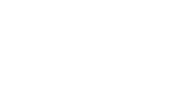ハゲタカ学会/ジャーナルの手口に騙されないための対策とは
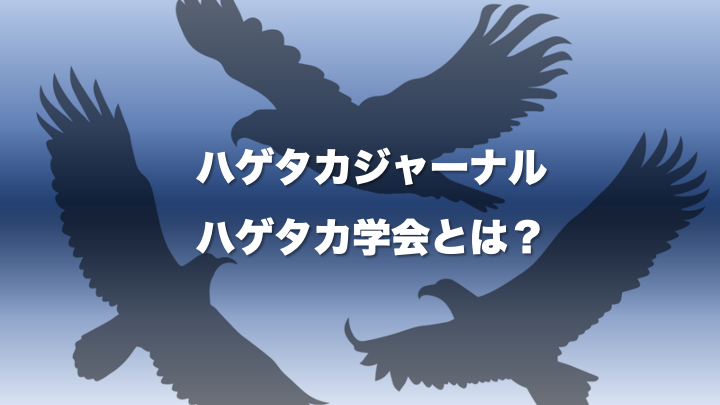
ハゲタカ学会/ジャーナルとは研究者から論文掲載費や大会参加費を搾取しようとする悪質な団体です。
知らずに論文を投稿したり、大会に参加すると酷い目に遭うことも......。
今回は、そんな学会/ジャーナルの手口や対策をお教えします。
ハゲタカ学会/ジャーナルとは?
ハゲタカ学会(predatory conferences)とは
ハゲタカ学会(predatory conferences)とは査読のない運営の元で学術大会・集会を開催し、参加者から参加費用を募ろうと活動する団体です。分野を横断した学術的根拠のない大会で少しでも参加者を募り、高額な参加費を請求してきます。
しかしながら、一部の研究者は学術大会への参加実績を目的に論文を掲載してしまうことも。特に新型コロナウイルスの流行によりオンライン大会が増加し、国際学術大会にも参加しやすくなったことで、実績のために参加してみるとハゲタカ学会だった……ということもあります。研究者は、参加する大会が正当なものか判断する必要があります。
ハゲタカジャーナル(predatory journals)とは
ハゲタカジャーナル(predatory journals) とは適切な査読を行わずに論文を掲載し、著者から論文掲載料を搾取しようとする粗悪な学術雑誌や論文掲載サーバーを指します。論文掲載料を稼ごうとするため、投稿から短い期間で掲載されることが特徴であり、実績を目的に論文を掲載しようとする研究者も少なくありません。ハゲタカジャーナルに掲載された論文は正規の研究として認められません。加えて研究費獲得の際に不利になったり、研究者としての信頼を失う可能性もあります。
最近ではハゲタカジャーナルに掲載された新型コロナウイルスに関する研究が横行し、ウイルスやワクチンに関する不確実な研究成果が発表され問題となりました。ハゲタカジャーナル(学会)は学術の信頼を著しくそこねる不当な雑誌・サーバーであり、研究者はその手口や見極め方を知る必要があります。
ハゲタカ学会/ジャーナルの手口
ハゲタカ学会の手口
ハゲタカ学会もハゲタカジャーナル同様、営業メールを執拗に送り付け研究者を賞賛し持ち上げてなんとか大会へ参加させようとします。学術大会はおもにリゾート地で行われることが多く、大会の会場や宿泊地を豪華にし参加者に多額の料金を請求します。
ほかに学術大会の権威性を偽証することもあります。著名な研究者の基調講演の実施を匂わせる、有名な学会との提携があるように見せかけるなど、その手口は巧妙なものです。
また、学術大会を直前で中止し、参加費だけを集めようとすることもあるため、特に注意が必要です。
ハゲタカジャーナルの手口
インターネット上で公開され、誰もが無料で閲覧できる状態をオープンアクセス(OA)といいます。ハゲタカジャーナルは、著者がAPC(Article Processing Charge)と呼ばれる論文掲載料を払う仕組みのオープンアクセスジャーナルに紛れ込んでいる可能性が高いです。
よくある手口として執拗な営業メールがあります。「大変素晴らしい研究だ」「ぜひジャーナルに掲載してほしい」などと研究者を賞賛し、その気にさせて高額な論文掲載料を徴収しているのです。
また、一見他のジャーナルに比べて安価な掲載料だとしても、雑誌のカラー掲載代金やオープンアクセス利用料などと称して追加料金を請求する場合もあります。
さらには、著名な研究者の名義を勝手に使う、権威のあるジャーナルの名前やロゴを模倣し正当性を偽ることも(いわゆる「偽サイト」です)。
特に経験の少ない若い研究者が対象とされることが多くありますので、聞いたことのないジャーナルへの掲載依頼が来た場合は、そのジャーナルを知っているか周囲の人に確認してみてはいかがでしょうか。
ハゲタカ学会/ジャーナルのデメリット
ハゲタカ学会に出席するデメリット
ハゲタカ学会への参加にも以下のようなデメリットがあります。
・高額な学会会費、大会参加費の請求
・急な大会延期または中止により参加費のみを不当に請求される
・ハゲタカ学会の関係者と認識され信用を落とす
・査読や議論がなく研究成果の発表が十分にできない
ハゲタカジャーナルに掲載するデメリット
ハゲタカジャーナルへの掲載には以下のようなデメリットがあります。
・査読が実施されないため、正規の研究成果と認められない可能性がある
・ハゲタカジャーナルへの掲載実績から研究者としての評価が下がる
・論文受理後に追加で高額な掲載料を請求される
・論文の取り下げができず、他の雑誌に投稿できなくなる
・雑誌の廃刊やサーバー終了にともなう研究成果の消失
・不備のある論文が社会に出回り引用されてしまう
一部には業績を作るためハゲタカジャーナルと知らずに投稿したり、学会に出席したりしようとする人もいます。しかし、業績を作るつもりが逆に研究者としての信用を落としてしまうこともあるのです。これらのデメリットがあることを認識し、信頼できる出版社や学会かどうかをよく確認しましょう。
ハゲタカ学会/ジャーナルかも?見分けるためには
学会はココで見分けよう
ハゲタカ学会の特徴の一例です。
怪しいと思ったらこちらを参考に学会や大会の情報を確認しましょう。
・連絡先の情報がない
・不自然に豪華な大会会場
・登壇者や主催者に実績がない
・過去に開催実績がない
・参加費の払い戻しに関する記載がない
・扱う研究範囲が広すぎる
ジャーナルはココで見分けよう
ハゲタカジャーナルの特徴の一例です。
怪しいと思ったらこちらを参考にジャーナルや出版社の情報を確認しましょう。
・Emailでの執拗な勧誘
・掲載料に関する詳細な記載がない
・査読のシステムが不明確
・投稿から掲載までの期間が極端に短い
・編集責任者が明記されていない、または実績がない
・論文撤回に関する記載がない
(偽サイトの場合)
・webサイトに著しい不備がある(多すぎる誤字脱字・文法の誤り等)
・公式機関が注意喚起を出している
ハゲタカジャーナルを見分けるならこちら!
(1) Think.Check.Submit 日本語サイト
「Think.Check.Submit」は研究者をハゲタカジャーナルから守ることを目的としたサイトです。信頼できるジャーナルを掲載するオープンアクセス学術誌要覧(Directory of Open Access Journals:DOAJ)に登録されているか、出版社が出版規約委員会(Committee on Publication Ethics:COPE)やオープンアクセス学術出版社協会(Open Access Scholarly Publishing Association:OASPA)に登録しているかなどをチェックリスト形式で調査することも可能です。 ジャーナルの信憑性を確かめる際にご利用ください。
(2)Directory of Open Access Journals:DOAJ ,Scoups
DOAJやScoupsとは、オープンアクセス誌を検索することができる論文データベースです。厳しい審査基準をパスしたジャーナルだけを掲載しており、信頼できるジャーナルを集めたいわゆる「ホワイトリスト」となります。
特にDOAJは、定期的に掲載されるジャーナルが更新され、審査に通らなかったジャーナルは採録がとりやめられるため信頼性は高いと考えられます。
DOAJについての詳細は以下の記事をご覧ください。
(3)Beall’s List of Potential Predatory Journals and Publishers
Beall’s Listはハゲタカと疑われる雑誌や出版社が記載されているリストです。アメリカの大学附属図書館の司書を務めていたJeffery Beall氏が2017年まで公表していたものを、現在は匿名研究者が引き継いで公開を続けています。
しかし、このリストにはホワイトリストに掲載されているようなハゲタカジャーナルではない雑誌・出版社が含まれていると指摘されています。不正確な部分あることを考慮し、他の情報源と照らし合わせて使用しましょう。
(4)Web of Science
Web of Scienceは、自然科学・科学技術分野の研究論文の引用と影響度を評価するための主要なデータベースで、インパクトファクターを提供します。インパクトファクターとは、特定の期間内に発表された論文が平均してどれだけ引用されたかを測定することで、学術雑誌の影響力を表す指標の1つです。
学術雑誌の信頼性と権威を評価する便利なツールですが、中にはインパクトファクターに似た偽の指標をインターネット上に公開している悪質なハゲタカジャーナルも存在します。複数の見分け方を参考に判断するなど注意しましょう。
Web of Science についてはこちらの記事をご覧ください
(5)その他の有償契約サイト
各大学や学会等の機関でもハゲタカジャーナル(学会)について説明・注意喚起をしているwebサイトは多くあります。一部の大学では、ホワイトリストを見ることができるサイト等を有償契約していることもあります。ご自身が所属する研究組織がアクセスできるサイトも有効活用するとよいでしょう。
学会のことならSOUBUN.COM
ハゲタカ学会/ジャーナルは研究者の貴重な資金と時間を狙う存在です。
今回お伝えした情報をもとに、ハゲタカジャーナルやそこに掲載された論文に注意しましょう。
SOUBUN.COMは、学会をお客様としてきた80年の歴史があります。
現在は学会事務局代行・学術誌発行サポート・学術大会支援・学会HP制作など幅広くサポートしています。
査読管理や電子ジャーナルへの投稿サポートも承っております。
詳しくは以下のお問い合わせフォームからご連絡ください。