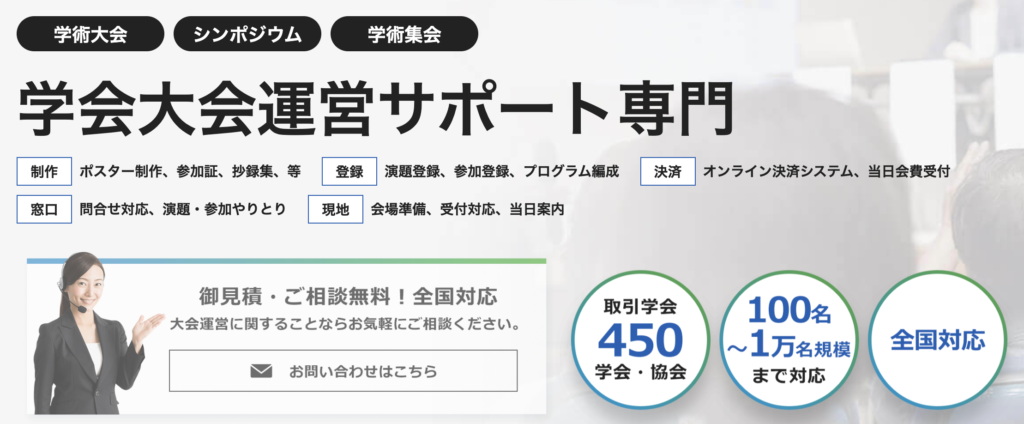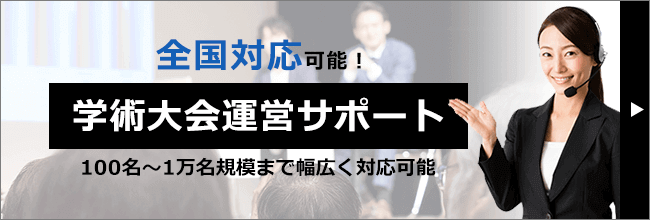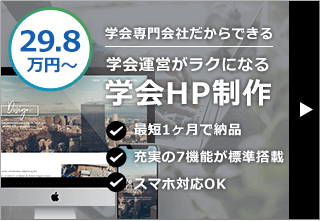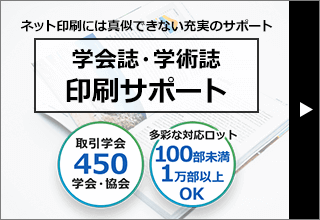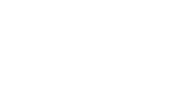学会の市民公開講座<方法を解説>

学会が市民公開講座を開催することで、一般への啓蒙活動や学術分野の発展を狙うことも可能です。
一方、参加者の満足度や集客、案内方法等、実際に行う上での課題もあります。
今回は学会が市民公開講座を成功させるためのポイントをお伝えいたします。
学会に市民公開講座は必要?
大会や総会と合わせて行われることも多い市民公開講座。学会にとって、市民公開講座を重要視するか判断が分かれるところでしょう。しかし、以下の2つを目的に市民公開講座を有効に活用している学会もあります。
①市民への啓蒙活動
学会が危機感を持っているテーマについて、一般市民はよく知らないことが多々あります。
医療分野はその最たる例でしょう。がんや心筋梗塞等の疾病のリスクや予防の方法、早期発見の重要性等を学会が提唱しても、人々に伝える術がなければ意味がありません。
市民公開講座によって情報を発信できれば、参加者やその友人・家族への啓蒙活動が行えます。
②研究分野の発展
学会が市民公開講座を行うことは「新たな研究人材の創出」と「研究者のモチベーション向上」に繋がります。
研究内容を一般に公開することで、参加者へ研究に興味を持つ機会を提供できます。そうして、市民公開講座をきっかけに研究者を目指す人もいるかもしれません。
加えて、研究内容に対して参加者が「面白い」「楽しい」と思ってくれることは、研究者のモチベーション向上にも繋がります。一般の方に研究内容の面白さを伝えることは、研究分野のやりがいや魅力を再確認する良い機会となるでしょう。
学会の市民公開講座の企画
一般への啓蒙の場合
啓蒙活動を目的とする場合、重要なのは「当事者意識」を参加者に持たせることです。
疾病や災害が自分に起こる確率は低いため、多くの人はどこか他人事と考えてしまい危機感を持ちません。人々の心に訴えかけるには、問題を自分事として捉え危機感を持ってもらう必要があります。
医療系の講演であれば、実際の患者の例を紹介しリスクを強調する、病気に繋がる習慣を指摘し参加者をドキッとさせるのが効果的でしょう。
もちろん、ただ不安を煽るだけではいけません。早期発見の重要性や治療方法等をお伝えし、参加者に安心してもらいましょう。
また、講座の中で次の行動を提示することも大切です。健診や防災グッズの紹介等、講演を聞いた後の具体的な対策を伝えれば参加者が行動する確率は高まり、より実のある講座となるでしょう。
研究情報を発信する場合
研究に関連する情報を発信する場合、「親近感」を意識すると良いでしょう。
一般の方から見れば学会の研究内容は難しく、なかなか興味を持つのが難しいかと思います。そこで、学会の研究内容を参加者のよく知る身近なテーマと結びつけると効果的です。
例えば経済系の学会の場合、「寡占市場における均衡状態」よりも「なぜ携帯会社の料金は高いの?」の方が、より身近に感じられます。
また、実際にその研究を体感させることも有効です。ただ聞くだけではなく、研究中の物質に触れてみる、新しいテクノロジーを体験させる、心理学の効果をクイズや会話を通じて再現する等、その研究を体感することでより満足度の高い講座に繋がるのではないでしょうか。
学会の市民公開講座の集客
興味を引くテーマを強調する
集客において大切なのは、一般の方が「聞いてみたい!」と思うわかりやすいテーマを作ることです。講座の内容や目的を一言で表すと何になるのか、参加した人にどんな感情を持って欲しいのか、考察した上でテーマを設定しましょう。
その中で意識すべきは、先に記した当事者意識や親近感です。この二つを用いることで、参加者は「もしかしたら私も……」「それ気になる!」といった感情を持ちやすくなります。
また、参加を案内するポスターやデジタル広告をデザインする際、開催概要や申込・登録方法よりもテーマを強調することが大切です。「第〜回 専門医による感染症の解説」といったタイトルを強調しても、人々は興味を持てません。最も人々の興味を引くテーマを強調することが大切です。
学会のポスターや広告デザインのコツについては、2022年12月に開催された「病院マーケティングサミットJAPAN2022」でも解説されています。
【学会共創2022】えっ!これ本当に学会ポスター?
〜心ときめく学会メインビジュアルの創り方〜
https://youtu.be/gOBbWEUPd8g?t=11037
ターゲットに応じたメディア
広告を打つ際には、どのメディアにどれくらい予算を費やすかプランを組む必要があります。
集客において広告の重要性は言うまでもありません。より多くの広告を打ち出し市民公開講座を認知して貰えば、それだけ多くの参加者を見込めます。
しかし、学会の予算には限界があります。限られた予算内で集客を成功させるために、ポスターやデジタル広告、DM等の様々な手段がある中でターゲットに応じてメディアを選択しましょう。
例えば若者をターゲットにする場合、ポスターやDMよりもSNSを利用したデジタルマーケティングが効率的でしょう。逆に高齢者をターゲットとする場合、ビラを投函するポスティング広告が有効です。
学会の市民公開講座の注意点
利益相反(COI)への配慮
学会での演題発表のときと同様、市民公開講座においても演者から利益相反(COI)について説明する必要がある場合もあります。
プログラム開始前に利益相反の情報を開示する、演者から講座のスライド内に利益相反の開示をするよう依頼する等して対策しましょう。
インターネット上での公開
会場の映像やオンラインで行われた講座を録画し、インターネット上で公開することもあるでしょう。予定が合わずプログラムに参加できなかった人も視聴できることや、情報発信を動画を通じて行えるといったメリットがあります。
一方、公開方法には注意が必要です。例えばYouTubeで公開をする場合、参加料を集める市民公開講座の公開は推奨しません。YouTubeでは営利行為の発生する動画の公開は禁止されており、有料講座の公開はこの規約に抵触する恐れがあります。また、視聴者の顔が映り込んでいる場合は肖像権に抵触する可能性もあります。
インターネット上で講座を公開する場合、投稿方法や利用するサイトには十分注意しなければなりません。
学会の市民公開講座事例
日本循環器学会
日本循環器学会は2022年、「健康ハートウィーク2022」を開催し、多くの市民公開講座を実施しました。
夏休みの自由研究を題材にした「すごいぜ心臓 小学生の心臓教室」、医学部志望の学生に向けた「集まれ!未来のドクター」、一般市⺠を対象とした「地産地消・減塩レシピ対決」等、参加者が興味を持つテーマを題材に循環器に関連する情報を各種発信し、啓蒙活動や教育機会の創出を実施しています。
多くの学会はここまで大規模なイベントを実施することは難しいかと思いますが、ターゲットやテーマの設定は参考になること間違いありません。
健康ハートウィーク2022のリンクはこちら(https://j-circ-assoc.or.jp/approach_posts/765/)
日本数学会
一般社団法人日本数学会では、年に2回一般向けの講演会を実施しています。
大学や大学院レベルの数学という一般の方には難しい題材ながら、2021年の講座では一般市民にとって身近な「宝くじ」をテーマに講演をしていました。
講演の軸を参加者の興味に寄せつつ、学術分野の面白さを伝えている事例です。
日本数学会ホームページのリンクはこちら(https://www.mathsoc.jp/)
学会の市民公開講座ならSOUBUN.COM
株式会社ソウブン・ドットコムは学会サポート企業として80年の実績があります。
オンライン開催の講演サポート、講座のオンデマンド配信、イベントPR等市民公開講座に関わる様々な業務をお手伝いいたします。ご興味のある方は、お気軽にご相談ください。